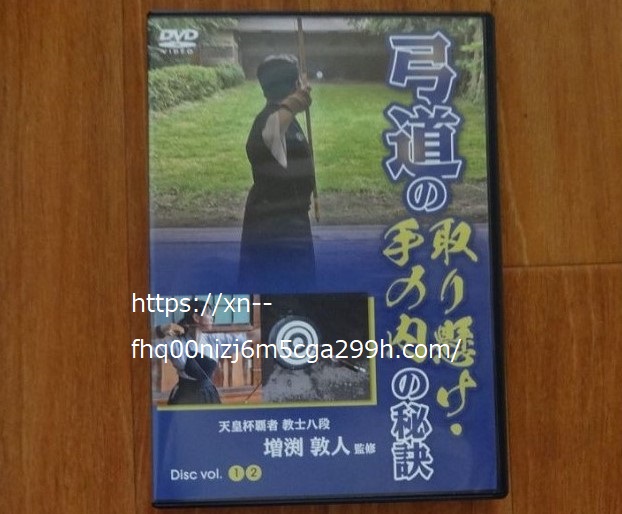取り懸けに違和感があるならゆがけの中の指に注目しよう
「取り懸けに違和感がある」なんてこと、ありませんか?
取り懸けは右手に矢を取り添えて弦を持ち弓を引く用意をすることですが、基本の形は弦を人差し指と親指で挟むこと。

取り懸けが自己流になっている人もたまに見かけますが、正しくきちんと行わないとスムーズに離れを行うことができなくなります。
そんな取り懸けはゆがけ帽子の向きだったり、押さえ方、矢や筈の位置など注意すべき点は色々ありますが、違和感があるという人は、ゆがけの中の指に注目してみると良いです。
人差し指と中指は、第二関節を意識して、指に力を入れてゆがけ帽子を握ったり、押さえるのは良くありません。
指を曲げて握ってしまうと、離れにくくなってしまうので、指は軽く伸ばした状態にしておきます。
親指も軽く伸ばしておきます。親指を曲げてしまうと握り込んでしまう形になってしまい、この状態で離すことは難しくなります。
また、綺麗な離れが出ずに手が開いてから離れるということになりかねないので、そういった意味でもできるだけ人差し指と親指の又を狭く使うようにしたほうが良いです。
手の内の力加減は電車やバスのつり革を持つときの形のが理想と言われるので、人差し指や中指の第二関節に意識を置いて、指先に力を入れてゆがけを握るのはやめましょう。
人差し指、中指、あるいは薬指の三本の指は1枚と考えたほうがいいかもしれませんね。
また、筈の位置ですが、できるだけ人差し指と親指の又の奥の方にセットしておいたほうが良いと思います。
この状態で弦を挟むと人差し指で矢を押さえることができます。
人差し指が矢にしっかり付いていれば、引いている途中で矢口が開いたり、矢が落ちるということはなくなるからです。
また、取り懸けは三つゆがけと四つゆがけで行いますが、親指の上に乗るのは、三つの場合は中指、四つの場合は薬指が乗ります。
いずれにしてもに取り懸けというのは、自分で安心して取り懸けた状態で離れやすいというのが理想です。
この取り懸けた形は、打ち起こしても引き分けても、会に入っても形が変わらないようにします。
実際には弦に引っ張られるので多少形はかわりますが、自分の感覚の中では形は変わらないようにしておくのが取り懸けのコツです。
取り懸けに違和感を感じないためにも、正しい基本の取り懸けのやり方をマスターしましょう。
待望の中級者向け!弓道DVDがリリース!
関連ページ
- 足踏みのコツ
- 胴造りのコツ
- 弓構えの留意点
- 取懸けの手順
- 手の内の作り方
- 物見の手順
- 打ち起こしの高さ(角度)と手順
- 引き分けと大三の留意点
- 会の構成の留意点
- 離れのコツ
- 残心の重要性
- 早気の直し方
- 弓道の練習で出来るマメ
- 大三以降の引き分けのコツ
- 狙いのつけ方(的付け)
- もたれを克服するには?
- 口割りが低くなってしまう
- 平付けを改善するには?
- 顔向けの不正
- 顔を打つ
- もたれの技術的要因
- 胴造りの重要性について
- 詰め合いと伸び合いとは?
- 羽引きと円相の構え
- 弓道の押手について
- 会の意識とは?
- 引き分けができない
- 利き目の調べ方
- 大三から引き分けの留意点
- 弓構えで人差し指に力が入りすぎる
- 取り懸けのやり方と矢の位置
- 取り懸けの親指と弦の位置
- ゆがけの使い方の押さえてきたいポイントとは?
- 良い射のイメージを持つことが上達の近道
- 手の内の射癖!大三で崩れるのは?
- 会で射癖を生じさせない意識するポイント
- 打ち起こしの射癖!意識する感覚とは?
- 物見の射癖!狙いの見え方も変わってくる
- 引き分けの射癖!会に入る前のチェツクポイントとは?
- 離れの馬手について!理想は自然に見えること
- 引き尺がとれない、足りない
- 離れでのひねりの力について
- 弓道の大会で緊張・あがりはなぜ起こる
- 中押しのポイントとは?上手くできないなら、、、
- 行射動作とその確認には時間が必要?!早気の解決を困難にしているものとは?
- 残心の形!意識するポイントとは?
- 的の見方と弓手の動きの関係!的中率を上げる狙いのつけ方とは?
- 射の運行イメージを持って練習すれば的中率も上がる?!
- 離れ(狙い)の悪癖の直し方
- 肩や肩甲骨の動きについて!肩が上がる矯正法とは?
- 上級者を目指すなら守破離を旨としよう
- 弓手の手の内と弓!注意点と押さえておくべきポイントとは?
- 【何秒必要?】会は考えることではない!体の感覚でイメージしよう!
- 口割りが低い!直し方と練習法とは?